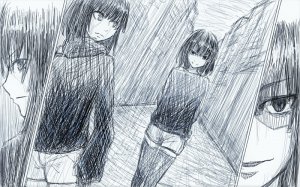小説『Endless story』#5-4
- 2016/12/07 08:12
- カテゴリー:ゲーム, Endless story, 小説, PSO2
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#5-4【見上げた夜空の星達の光】
重力と絶対零度を操る、ダーカーの王が一角「ダークファルス・【巨躯(エルダー)】」。
かの強大な存在が放った攻撃によって、惑星・ナベリウスの一部は今でも溶けることのない永久凍土が覆っている。
それはもう数十年も前の話で、ただでさえ原生種の生命力と適応力とが強いナベリウス、今では独自の生態系が築き上げられるまでに至っていた。
実際に、そんな短期間で生態系まで変わるモノだろうかとも考えたけれど、そういえばここは宇宙だったなあ、なんて思い出す。
「わっ……な、なんか釣れました!」
「それは『凍土ワカサギ』だにゃ。塩焼きにして食べると旨いから、このあと晩飯
の足しにでもするといいにゃん」
「どうせだから、今から火の準備をしておこうか」
「お父さん、私も手伝うわ」
「ラ・フォイエで着火しまひょか?」
「サモナーといえど、焚き木ごと爆散する気がしますね」
――どういう流れだったか私たち一行はそのナベリウス・凍土エリアで、ギャザリングに興じる運びとなっていた。
アークスとは惑星間を飛び回り、ダーカーの殲滅とともに、惑星の調査も行う集団だ。そのため時には惑星の生命体や物質からサンプルを採集し、実態を研究する必要もある。そして、ただでさえ途方もない人数の住人を抱えた船団なのだ。食料の供給源は、あればあるほど困ることは無い。
そこでアークスによる食料や鉱物、その他多様な生物や物質の採集が行われる――それが「ギャザリング」である。
ちなみに地球では、コンクリートをピッケルで採掘することによって「なぜか」大豆やワサビなどが発掘されるらしい。なぜか。
ワカサギを開きっぱなしのPREボックスへ放り込み、ふたたび釣り糸を、くり抜いた氷原の穴へ垂らしてから、空を眺めて考え込む。ルベルは何の目的で、私をギャザリングへ誘ったのだろうか。
こちらから問おうにも……なんとなく気まずく、どんな風に私から彼女へ話しかければいいのか分からなかった。
そんなこんなで、アリシアと並び立ちながら、呆けて立ちすくむナベリウスの夜。
地球に居た頃は、人気があって騒がしいという場所というものが、とにかく嫌だった。しゃべって、周りの雰囲気に乗って、話題を提供して、盛り上がらなければ、まるで自分の存在意義も、価値も、どこにもないと言われているようで。
自分は居て良いと口先では言われても、やはり見直してみれば、自分が居ていい場所はどこにも無いと、決定的に叩きつけられているようで。
だから、改めて私は悩み始めていた。
私は本当にここに居て良いのだろうか。
どうして、この人たちはここまで私に良くしてくれるのだろうか。
――どうして、私は、この喧騒の中に居て、ちっとも不愉快じゃないのだろうか。
「……世界群歩行者達ヘ来てから」
アリシアが、やおら話し始める。
「いろんな人たちと出会って、私はすごく救われたんです。地球では、友達を作ることも出来なかったから」
きっと本来は照れ屋で、内気な子なんだろうということは、すぐに見抜けた。
そんな彼女が、どうして私なんかに話しかけるつもりが起きたのだろう。
「ひとりで抱え込まなくても良いんだって、初めて思えました。私は自分から話しかけるのが、すごく苦手で……でも、皆さんは私のことも気にかけてくれる」
それは、分かる。
本来ならば放っておいてもいいような私のことも、みんなは放っておかなかった。この3日間も、ちゃんと毎日欠かさず、料理を持ってきてくれたのも、不思議で、慣れなくて、なぜだか少しだけ温かいように思えて。
「だから、私が受けた恩を、少しでも何かの形で返したくて……たとえば、もし地球から私みたいにオラクルへ来た人が居たら、何か悩んでいたら……自分がそうして貰ったように、大丈夫ですかって声をかけてあげたくて」
ああ、そうか。
それで彼女は、と気付き、同時にアリシアがこう言った。
「ロビーで歩いているユカリさんが、とても辛そうで、失礼かもしれないけれど、地球に居た頃の私と重なって見えたんです。そういう時に――誰か頼れるヒトが居るってだけで、どれだけ救われるか、よく知っていますから」
今日まで私とアリシアは、互いに話したことも無かった。
彼女にとって「私」を心配したり、助けたりするような、特別な理由はどこにもない。実際、私もまさか誰かが手を差し伸べてくれるだなんて、少しも期待していなかった。
お母さんですら私を突き放すのに、誰かが無償で気にかけてくれるワケがないと思っていた。他人は誰もが私に少しも興味を抱いていないと、ずっとずっと思っていた。
「知り合ったばかりの私を、頼ってと言っても、きっと難しいと思います。も、もちろん私は頼られれば嬉しいですけれど……。私でなくても、皆さんはいい人たちばかりですよ。だから……何を悩んでいるのかまでは分かりませんけれど、あまり1人で思い詰めないでください」
それを言うために、彼女は勇気を出して、私に話しかけてきたのだ。あんなに必死で、精一杯に。
目頭に熱いものが込み上げてくる。胸の奥から、小さな光の泡が、次々に沸き溢れては弾けていった。
かつて自身がそうされたように、自分もだれかに優しくしたい――それだけでヒトは、しかも私と同じくらいの女の子が、勇気を出せるモノなのか。
そして、その優しさが私へ向けられていると、はっきり認識した途端に……チャレンジクエストを終え、みんなとご飯を食べたあの時のように――涙が、頬を伝って止まらなくなった。
なんて優しいんだろう。