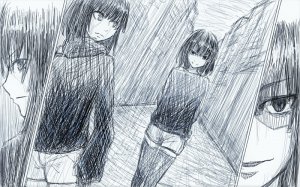小説『Endless story』#10-3
- 2017/07/26 10:48
- カテゴリー:ゲーム, PSO2, 小説, Endless story
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#10-3【"IDOLA" The Strange Fruits】
切っ先三寸で撫ぜるように。
エルダーが放った凶悪な質量の横薙ぎは、その軌道を大きく逸らされた。引き続いての掌底も同じように、逸らし躱す。ひとつひとつが必殺の重量を誇る巨腕、それが千手観音よろしく何本も、何本も、何本も。
単独でウィリディスは、エルダーの攻撃を凌ぎ続けていた。
最低限の力で最大限の効果を。切っ先で逸らし。鎬で流し。柄で弾き。ともすれば瞬時に潰され肉塊とされかねない程の攻撃を、全て最大効率で避けて受け流す。表情ひとつも変えずに、ただひたすらに眼前を見据えて。
しかし構わずエルダーの巨腕が迫る。これもウィリディスは避けようとする。しかし、当てが外れたのか一撃は彼の真横を過ぎて遥か後方へ。
……――いや違う、と気付く。
狙いを外してなどいなかった。エルダーの腕が揚陸艇をがっしりと掴まえる。更にまた何本もの腕が、がっちりと固定して離さない。そして空が覆われた。それも違う。頭上に迫って来たのだ……――エルダーの巨体が。
「ウィリディス!」
とっさにクロキンの叫びが響いた瞬間と、ウィリディス乗る揚陸艇が砕け散った瞬間は、ほぼ同時だった。
粉砕と同時に揚陸艇は火柱を上げ、粉々の残骸を地上に降らせてゆく。受け流す余裕はもっての外、逃げる隙も無いまま。
彼は間違いなく、跡形もなく圧し潰されたハズだった。
♪
A.I.S.-NTは果たして、アプレンティスの直前まで潜り込んだ。
しかし相手はあまりにも巨大。A.I.S.の大きさをもってしても、その差は比較にならない。ゆえに狙うは一点突破。立ち塞がる障害だけを斬り払い、地力の差で押される前に、目的を遂行する。
その目的はアプレンティスの打倒でも、社長の救出でもなかった。なぜなら――……。
「さすがにここまで来ると、敵さんの弾幕もえげつないなっ!」
「頑張って、ここでいいところ見せれば有給増えるわよ!」
「もうマイナスまで食い込んでるんであんま意味無い気が……っと!」
襲い来る何匹ものプチダモスをまとめて斬り払っている隙に、貫かんと本体から伸びて迫る青黒いレーザーを飛び退いて避ける。
退いた瞬間、アルーシュの杖から放たれる光条。更に波がごとく群れて飛び来る雑魚を薙いで、A.I.S.-NTの活路を開く。
乗じてA.I.S.-NTは前方へ発進するが、直後の光景にホールとアルーシュは目を見開く。アプレンティスの全身が細かく蠕動する。その中央部から黒い塔にも思える、巨大な口吻が伸びてゆく。その先端に、エーテルが集約してゆく。
「営業君、アレは……!」
「分かってますよ! けれど、いくら何でも早いなあオイ!」
アプレンティスがその口吻から放つレーザーは、砂漠の惑星・リリーパにある採掘基地までもを一瞬で消し飛ばす。それが市街地のド真ん中で放たれたらば、どうなるかは想像に難くない……いや、想像もできないだろう。
A.I.S.-NTは携えていた武装をダブルセイバーから、肩部に背負っていた巨大な大砲へと持ち替えた。しかしそれは大砲と呼ぶにはあまりに砲身が短く、巨大である。
「今回の取引相手にゃ大出血特別サービスだ、試験運用ついでにコイツも喰らってけ! 当社自慢の新製品――……」
チャージを続けるアプレンティスの口吻に、その銃口が差し向けられた。
反動に備え後方に逆噴射を行いながら、銃口に可視化……いや固形化するほどに高密度のフォトンが凝縮されてゆく。
A.I.S.-NTとは、遠距離への対応力を下げる代わりに、極限まで至近距離での火力を追求したモデルである。その仕様を詰める際、まず問題となったのは「フォトンブラスター」に替わる武装をどうするかであった。
フォトンブラスターとはA.I.S.が持つ最大の兵装と言っても差し支えない。多くの回数を使えない代わりに、最大の火力で最広の範囲を灼き尽くす、圧倒的火力のレーザーカノン。しかし同時に、最もA.I.S.-NTの「無用な被害をもたらさず、かつ圧倒的な火力を維持する」コンセプトに反する武装でもある。
そこでこんな提案が出たのは、ある意味では当然だった。ずばり「フォトンブラスターの火力を、一点に凝縮させるのはどうか」と。
この武装は飛距離を持たない。しかし代わりに対ダーカー兵器としてこれほどの火力は前例がない。アークスの最高峰が振るう最強の武器「創世器」さえかくやと言わんばかりの威力が、そして放たれる。
「フォトンバンカぁあああああ!!」
まるで惑星が脈打ったように劇的な音。
凝縮されたフォトンの槍が、凶悪な速度を伴ってアプレンティスの口吻に突き立つ。
フォトンの槍はアプレンティスの口吻を中ほどまで貫通し――そして内側から炸裂する。
パイルバンカーという兵器を元にデザインされた、A.I.S.による近接兵器の極致。高機動と極めて限定的な使用を前提にするA.I.S.-NTだからこそ成しえた、いわゆる浪漫砲。
それが「フォトンバンカー」である。
アプレンティスの巨体がのたうち、天も揺るがす咆哮が苦痛を示す。
「よっしゃ、ジャックポットだァ!」
「ええ、これなら充分ね――……」
思わずA.I.S.-NTと共にガッツポーズを決めるホールと、言いながらホログラム状の端末を取り出すアルーシュ。そして口元にインカムを当て、彼女は示し合わせたように言った。
「……――試験運用のデータは集まりました。社長、もう良いですよ」
言うが早いか、アプレンティスがひと際甲高い絶叫を上げる。
♪
透藤縁の具現武装は協力無比であり、とりわけ武力という点のみについては、現在確認されている中でも比類する例がない。たったひとりでアークス擁するチームを壊滅させることさえも、対峙の仕方を選べば確かに容易いだろう。
特に「アークスをダークファルス化」させるという能力については、敵の無力化と自身の戦力増強を同時に行える、あまりにも強力なカードだ。
彼女の思惑にひとつ誤算があったとすれば……まさしく喧嘩を売るには相手が悪かったという点に尽きる。
「一寸法師って知ってるゥ?」
キャンプシップの内部、アーテルがアルトに間延びした声で訊いた。
「知らにゃいにゃ。売れるのかにゃん?」
「地球伝わる童話らしくてねェ、今回の作戦にピッタリだわァと思ってェ」
アーテルは前髪の毛先を弄びながら、童話の内容をアルトに説明する。
親指ほども小さい勇敢な若い武士が、大きな鬼の体内に潜り込んで、鬼退治を果たす。地域や文化によって多少の差はあれど、この辺りのあらすじはそこまで大きく変わらないだろう。
「なるほど。つまりは、やっぱりデカブツは内側から崩すに限るって話だにゃん」
「ええ。だからルベルは透藤縁に自分を攫うよう差し向け、それを社長もまたそれに便乗したっていうコトねェ」
「でも、今回はどっちが怪物だか分かったモノじゃないにゃん」
何しろルベルも社長も、その内にダークファルスを飼い慣らしている怪物だからだ。
♪
絶叫の原因は、アプレンティスの頭部から生える黒い剣だった。
否、生えているのではなく、内部から貫通していた。黒い剣は無理やりアプレンティスの頑強な外皮を内側から切り裂き、傷口を拡げてゆく。
切り開かれた傷口から現れた人影に、DFco.の面々は見覚えがあった。待ち望んでいた。彼は束ねた薄紫の髪を揺らし、ジッポを鳴らし煙草に灯を点け、射殺すような鋭い眼光で辺りを一瞥する。
「対幻創種兵器の開発に、何か参考になるかと考え……私自らこうして出向いてみたが」
憮然と、悠然と、そして不機嫌そうにアプレンティスの内部を突き破って現れたのは、DFco.を統べる社長その人だった。
「所詮、紛い物は紛い物だな。この程度で私を束縛できるとでも思ったか?」
DFco.の面々の目的は、アプレンティスの打倒でも、社長の救出でもなかった。なぜなら、その必要はどこにも無いからである。
かつて自分の意志で本物のダークファルスを捻じ伏せ、自身の支配下に置いた社長が、エーテルで形作られた模倣ごときに支配されるワケもなかったのだ。
一撃必殺のフォトンバンカー、社長の内部からによる奇襲を受け、最早抜け殻となったアプレンティスの巨体が大きくバランスを崩す。その際に巨大な触手がA.I.S.-NTに向けて猛然とした勢いで伸びてゆく。
「――ッ」
「秘書さん、危ないッ!」
普段ならいざ知らず、フォトンバンカーを発動した直後で、A.I.S.-NTは緊急回避のための余力も残されていない。
そしてA.I.S.-NTならばともかく、あの一撃が秘書に当たればただでは済まない。
しかし。
「油断し過ぎだ」
触手はバターのように寸断され、そして斬り飛ばされる。
さらにその衝撃が余波を生んでアルーシュはバランスを崩して倒れ込みそうになるも、社長が右腕で彼女を抱き止めた。
社長は一瞬でアプレンティスの上部から降り立ち、そして左手に握る黒い剣で、触手を斬り落としたのだ。
腕の中で抱かれながらアルーシュは目を丸くして、次にため息をつきながら微笑んだ。
「社長を信じていましたから」
「……下らん」
仏頂面で鼻を鳴らし、無造作にアルーシュを手放す社長。いきなりだったものでまたも転びそうになったアルーシュは口を尖らせて抗議の視線を向けたが、どうやら社長は取り合うつもりもないようだ。
社長はジャケットを投げ捨て、核を失ってなお最後の足搔きとばかりに暴れるアプレンティスを見上げる。アルーシュもひとつ瞑目してから表情を切り替え、長杖を構え直す。ホールが搭乗したままのA.I.S.-NTも武装をツインダガーに持ち替えた。
さらに面々の足元に、黒い水溜まりのような、円形の闇。
闇の中から音もなく現れたのは、クラリスと黒い女性型キャスト……――社長の護衛、アヴリスの姿だった。
クラリスは両手に暗器を構え、アヴリスは黒い骨格のような強弓に矢を番える。
「後方はどうなっている?」
社長が振り返りもせず、クラリスに聞いた。
「M隊とW隊が派手に暴れまわっているお陰で、ひとまずは落ち着いているネ」
「ならば、まずは往生際の悪い客の接待と行こうか。さあ――存分にもてなしてやれ」
社長がジャケットに続いて、煙草を投げ捨てる。それが蹂躙の合図だった。
♪
エルダーの腕に降り立つ音。
揚陸艇と共に圧し潰されたハズのウィリディスが、そこに居た。
すぐ叩き落とさんとばかりに、別の腕が彼をめがけて振り下ろされる。彼は持ち出した導具を、何もない虚空にめがけて投げる。
そして巨腕が振り下ろされたと同時――その姿が消える。
消えて――現れる。導具を投げた軌道上、何もない虚空に。
全身を重力に任せ。頭から自由落下する体勢のまま。
「お前に俺は殺せない」
今度は武装を双機銃に持ち替え。今の隙を狙わんとばかりに迫っていた腕を撃ち抜き。撃った反動で宙を舞い。また新たに襲い来る腕までも撃ち落とし。再び導具に持ち替え。一気に数枚の導具を辺りへばら撒いて。
エルダーの腕が嵐のように連続して迫る。彼は導具を撒いた軌道線上で瞬間移動を繰り返し。全ての攻撃を避けながら。回転する光の刃で迎撃。
そして不意にエルダーの、赤く胎動するコアの眼前へ現れ――深々と大剣を突き立てた。
大地さえ割るような唸り声を上げて、エルダーが全身を傾ける。
ウィリディスは構わずコアへと顔を寄せて、まるで内部に居る誰かへささやくように、簡潔に言い放った。
「そろそろ良いぞ。出て来い――ステラ」
エルダーのコアを引き裂いて、飛び出したるは巨大な漆黒の腕。
まるで黒い甲冑を纏った悪魔のような腕だった。
それはルベルの中に息づくもうひとりの人格、人造的に作られたダークファルス。黒い悪魔はエルダーから上半身だけを現し、上空へ向かって6枚の大翼を広げる。
「――あはっ」
鈴が鳴るような、と形容すれば良いのだろうか。可憐な、それでいて底冷えするほどに恐ろしい「悪意」を孕んだ、少女の笑い声が聞こえた。
それは悪魔の、割れて内側の空洞が露わになった胸部から……彼女は嗤っていた。普段ツインテールに結んでまとめている、銀に毛先がマゼンタの長髪は振り乱されている。
左目は瞳以外が宵闇のように暗く、どこか歪な印象を与えていた。
「斯うして『外』へ出て来るなんて、何時以来かしら!」
漆黒のドレスを纏った、紅い瞳の少女・ルベル、いや……――ダークファルス・ステラは端整な顔立ちを凶悪に歪める。
彼女を中心として展開された黒い巨大な悪魔が、天に向かって雄叫びを上げた。するとたちまち上空を深い闇色の雷雲が覆って包み、街の東側全域に雨が降り始める。それらはただの雨ではなく、雲と同様の黒い雨だ。
ウィリディスがエルダーを相手に、ひとりで立ち回ることを選択した根拠は彼女だった。
ウィリディスはステラの監視役であり、抑止力でもある。翻って言えばウィリディスが容認し、かつアークスに害を成さないと判断される範囲で、ステラはその力を振るうことが容認されている。
そのため最初からウィリディスがエルダーに接近し、ルベルと接触した時点で、勝敗は決まっていたのだ。
ステラを呼び起こし、内側からエルダーを突き破ってしまえばいいのだから。
「差し当たっては、此の鬱陶しい柵(しがらみ)を取り払って仕舞いましょう」
ステラが中指を立てた。まるでそれが合図のように、悪魔の手がエルダーの腕を掴んで――いとも容易く引き千切る。
傾いていた巨体が倒れ込んでいく。間髪入れずまた別の腕も、さらにまた別の腕も次々に引き千切られる。ただでさえ核を失ったエルダーは一方的に蹂躙され、黒い悪魔と共に、青黒い光の粒子となってゆっくりと崩れ落ちてゆく。
黒い雨とエーテルの雪とが地上へと降り注ぐ中、ステラは悠然とビルの屋上へ降り立つ。ヒールの硬質な音を高く響かせて、漆黒のドレスから軽く埃を払う。ただならぬ気品さえ感じる所作を以て君臨した彼女の視線は、同じく背後へ降り立つ彼へと注がれていた。
人造ダークファルスの極致・ステラと、かつて単身で彼女を制したウィリディスが対峙する。交錯する歪な紅い瞳と、エメラルドグリーンの眼光。
ステラは挑発するように口角を歪め、彼をせせら笑う。
「唐突に淑女(レディ)を喚び付けて於き乍ら、厭いたら使い捨てる腹積もりかしら?」
ウィリディスは無言のまま得物を握り直した。それが何よりの返答だった。
黒い雨が降り注ぐ中、両者の間に緊張の糸が巡る。
しかしステラは唐突に彼をひとつ鼻で笑うと、ひらひらと手を振った。
「嗚呼、何て自分勝手な男(ひと)ね。今日は気分も好いし、貴方の事も気に入って居るから、大人しく従ってあげるけれど」
ただ、とひとつ前置きして。
「貸し一ツよ」
不意に、ステラは糸が切れたようにその場へ倒れ込む。同時に黒いドレスを模した装束が小さな幾羽もの蝶となって霧散し、コートを羽織った……元の「ルベル」としての姿に戻る。
ウィリディスは得物を投げ捨ててすぐさま駆け寄り、彼女を抱き起こす。
あまり時間はかからずにステラ……いや、ルベルは身じろぎして、薄目を開きながら、まるで寝ぼけているように彼の名前を呼んだ。
「ウィリディス……?」
「独断で無茶するな」
「……――信じていたもの。ウィリディス、あなたを」
遅れて、パラノイドサーカスの面々も同じ屋上へと駆け付ける。ナオキ、クロキン、後からギガント、魅月、プルート。
ルベルは「ごめん、ありがと」と小さく言いながら、自分で立ち上がる。ウィリディスもまた周囲の状況を見渡してから、改めて仲間たちの方へ向き直る。目下の脅威であったエルダーこそ消え去りはしたものの、まだ辺りには無数のI・ダーカーが飛び交っている。
ひと段落ついたものの、決定打になったワケではない。
「ナオキをはじめ、元パラノイドサーカス団員はここ東部一帯のI・ダーカー殲滅を継続」
「ウィリディス、お前はどうするつもりだ?」
クロキンの問いを受けて、ウィリディスは一度ルベルの方を見る。彼女はひとつ無言で頷いて見せる。そして前へ進み出ると、彼女は仲間たちに面と向かって告げた。
「わたしとウィリディスは、ユカリが居るK隊に合流します。きっとわたしたちは、彼女と透藤縁の決着を見届ける義務があるから」
♪
それは戦闘ではなく蹂躙だった。
ダークファルス・ルーサーとは、かつてアークスの前に立ちはだかった大いなる脅威であった。全知にも等しいとされる演算能力を以て、時間の流れさえも掌握する。フクロウと金時計を模した、荘厳とすら言えるほどの威容の前に、並大抵のアークスならば戦意を喪失して葬られてゆくことだろう。
だがabe-cが繰る一対の飛翔剣は堅牢で豪著な鎧を割り砕き。ロビットが放つ長銃の閃光は漆黒の腕ごとルーサーの握る剣を撃ち落とし。史記鏡が振りぬいた大剣の軌道は王冠を砕き散らし。曲がりなりにもダークファルスの一角を象った脅威が、為すすべもなく圧倒されてゆく。
「バーランツィオン!!」
そして振り下ろされる、光り輝く氷塔の刃。
マーミンが両手に携えた、氷属性と光属性の複合フォトンで構成された剣。その小柄な体躯からは想像も出来ぬ、巨体さえも押し切る勢いと破壊力。完全に巨体が揺らいだ隙に、さらに風属性のテクニック「サ・ザン」が撃ち込まれる。
事実上、アプレンティスとエルダーの相手はDFco.とパラノイドサーカスが務めており、なおかつそれらを無力化する秘策が……すなわち内部から囚われた本人を覚醒させて打ち破るという荒業が有った。
しかしロゼに限っては、虚空機関に囚われていたという過去があるものの、彼女自身はダークファルスなどではない。言ってしまえばいたって普通のいちアークスでしかない。
だからこそ、世界群歩行者達の精鋭たちがルーサーを相手取る担当として据えられた。
だからこそ、彼がこの場所の主役を担うことになった。
「ロゼぇえええええッ!!」
abe-c、ロビット、史記鏡、マーミンらによる怒涛の畳みかけを受けて、腹部の金時計を強引にこじ開けられたルーサー。味方たちによって切り開かれた道筋を、そのキャストは――ハイド・クラウゼンは、ロゼの父親は辿る。
尾を引くはコバルトブルーのフォトンライト。ただ一直線に、彼は駆け抜ける。
フォトンはアークスの「想い」の影響を強く受ける。
強い願いは奇跡を引き起こす、なんて陳腐な響きかもしれない。しかしかつて妻と娘を守り切れず、失意の海に溺れ、それでも立ち上がったハイドだからこそ知っていた。
意志の力こそが、望む運命を掴み取るための起点であるということを。
ルーサーと対峙するH隊の作戦は、圧倒的な火力で徹底的に外部を削り取り、それから内部に居る「彼女」へ、ハイドが接触するというモノであった。とても作戦とは言えないずさんな内容でこそあったものの、不思議なことに誰ひとりとして異を唱えはしなかった。
なぜなら――……。
「お父さん!」
……――親子の絆ほど断ち難いモノは、他にそう在りはしないからである。
ルーサーの開き切った腹部から覗く、底なし沼のような暗黒。そこから声から聴こえた。ハイドにとって何よりも愛おしく、何にも代えがたい、たったひとりの娘の声。娘が自分を呼ぶ声。差し伸ばされた腕は華奢で、折れそうで、しかし、だからこそ、ハイドは強く握りしめた。
そして引っ張り上げる。引っ張り上げて、抱き締める。彼女もまた、父親に抱き付いた。
「すまない。俺がついていながら、お前を危険な目に遭わせてしまった。助けに来たぞ、ロゼ」
「ううん、いいの。私は、お父さんを信じていたから……」
お互いの目をしっかりと見つめた。そしてロゼは、鋼鉄の身体を愛おしく抱き締めた。ハイドもまた、たったひとりのロゼを、応えるように抱き締め返した。
しかし無粋にもルーサーの抜け殻は、膨大なエーテルの残滓は、長大な漆黒の剣を握り、親子へ振り下ろそうと大きく振り被る。
ハイドとロゼは、ただ暴走するだけの巨塊を冷ややかに見上げた。ハイドはおもむろにルーサーの残滓へ向かって、人差し指を向ける。開かれたままの、金時計だった――漆黒の闇が露わとなっている腹部へ、青いマーカーが投じられる。
マーカーへ向けて、飛翔剣の、長銃の、大剣の、テクニックの――仲間たちの容赦ない乱舞が注がれる。剣を振り被る巨体はまたも後方へ揺らぎ、怯み、ハイドの反撃を許した。許してしまった。
左腕にロゼを抱き寄せながら、右手に構えられた長銃・ゼイネシスレーザーの銃口は、寸分違わずマーカーへ……ルーサーの腹部へと向けられていた。辺りの大気が震え、唸るほどのエネルギーが集約してゆく。集約し狙いを定め、そして放たれる。
核を失ったエーテルの巨塊が、魂を込めた一撃に耐えられる道理もなかった。
「――チェイン99『エンドアトラクト』!!」
巨体に風穴が空く。
想像を絶する衝撃が辺り一帯へと伝播したあと、一切の音は無かった。ただ巨体が剣を振り上げた体勢のまま、静かに制止しており、その腹部は拡がる漆黒の代わりに――巨大な風穴が空けられていた。
巨体ゆえにゆっくりと、青黒い粒子をまき散らしながら、しかし振動を伴わせてそれは沈んでゆく。ハイドも、ロゼも、H隊の面々も大げさにそれを喜びはしない。まるで予定調和だと言わんばかりに、粛々と各々が構えた武器の切っ先を下ろすばかりだった。
しかし、だからこそ、ロビットは眉を潜めた。マーミンも訝し気に目を細めて、ハイドも若干ながら驚く様子を見せた。
「あれは……!?」
abe-cが零した。核を失い、H隊のメンバーとハイドによるトドメを受けて打ち破られたハズのルーサー。
霧散してゆく残滓、その青黒い粒子――それらが、まとまって流れ始めたのだ。
粒子は意志を持ったように一点へ収束し、光輝く球体となり、そして飛び立とうとする。その方角は、紛れもなくユカリが居るK隊の、そして透藤縁が待ち構えていると目される、北の方角だった。
♪
私こと世界群歩行者達のメンバー・瑠璃恋詩(るりこいし)は回想する。
世界群歩行者達で保護されたばかりの彼女は、ただ頼りない、年相応な地球人だった。あるいは私もアークスになって居なければ、そうだったのかもしれないと思うほどに。
ただ彼女はチャレンジクエストでの、そしてナーシャによる訓練にも、ただひたむきに立ち向かった。自分が何のためにそうするのか。分からないまま、分からずとも、目の前の「自分が出来ること」へと愚直に立ち向かった。
ほどなくして、彼女自身がI・ダーカーを引き寄せるかもしれないということが、チーム内に対しても公表された。当然だが彼女自身も、自分が迷惑をかけているのではないかと、深く思い悩んだ様子だ。
しかしそれでも彼女は立ち直ったようだった。誰とどんなやり取りがあったのかまでは分からない。それでも次にチームメンバーである私たちの前に姿を現した彼女は、すでに覚悟を決めた眼差しだった。
それは自己犠牲を以てすべてを終わらせる、なんていう悲壮な決意に満ちた眼差しでもなかった。ただ「これから先に何が起ころうとも、全て受け止め、その上で自分が最善と思う判断に全身全霊を尽くす」――そんな意志が込められたような瞳だった。
たった一か月と少し。
それだけの間で、これだけの成長を遂げた彼女に、私は心からの敬意を払おうと思う。きっと、だからこそ私たちも彼女に力を貸そうと決意したのだろう。だからこそ私たちは、ここに立って居るのだろう。
そんなことを回想しながら、ダークファルス・ダブルの巨体は崩れ落ちていく。
トーニャ・モノリスは素性を明かさないが、アークスが公表した新クラス……サモナーとして随一の腕前を誇る。彼女が放ったマロンストライクで、ダブルの右前脚は砕かれた。
アリシアもユカリと同じように、本来はただの地球人の少女だった。しかし、その上でアークスとして活躍している腕前は伊達じゃない。彼女が放った抜剣の一撃は、右後脚を切り裂く。
ライレアはその言語野と引き換えに、膨大なフォトンを操る才能を宿した少女である。ダブルの左前脚を抜剣の一閃で、そしてすかさず左後脚を強弓で撃ち抜き、立ちはだかる城壁のような巨体の動きを封じる。
「チェイン50――『デッドアプローチ』『サテライトエイム』『インフィニティファイア零式』!」
団長による怒涛の連射が、崩れ落ち露わになったダブルの舌――その先で煌々と輝く、青紫のコアへと容赦なく放たれる。
そして、ここで全てを終わらせんとばかりの、彼女による一閃。
「……――グレンテッセン!」
彼女は、ユカリはI・ダークファルス・ダブル――透藤縁のコアを目掛けて、渾身の一撃を打ち放った。深く一息で踏み込み、思い切り振り抜き、息を吐き切って。
牢獄のように凶悪な口蓋から食み出した青紫色のコアは見事なまでに両断され、城壁を連想させる巨体は青黒い粒子をまき散らす。
「あっ……はあ、さすがにこの程度じゃ倒されちゃうかあ……」
背骨の奥から撫ぜるような薄気味悪い響きを孕み、透藤縁はぼやいた。
ユカリは、団長は、立ちはだかる面々たちは、あくまでも構えと警戒を解かない。今の戦闘も、決して容易な勝利だったワケではない。まだ透藤縁が何を仕掛けて来るか、何を企んでいるか分かったモノではない。
それらを覚悟したうえで、しかし私たちは戦慄せざるを得なかった。
「分かったよ、もう、分かった――……これが正真正銘、私の切り札だよ」
まるで無数に降り注ぐ流星群のように。
街の東側から、西側から、南側から、青黒いエーテルが塊となって飛来する。それらは一直線に透藤縁をめがけて取り巻いたかと思うと、漆黒の夜空を貫いて、そびえたつ闇の柱となった。透藤縁は両手を広げ、莫大な力の奔流へと身を委ねる。
膨大なエーテルの圧力に、私たちは身動きもままならない。
「ダークファルス『ごとき』がさぁ、奥の手だとでも思ってた?」
ただ足元を踏ん張って吹き飛ばされまいとする私たちの前で、透藤縁の「絶望」は像を結んだ。華美にも思える豪著な翼を広げた、白金色の巨人の姿。胸部には青紫色の巨大なコアが、まるでぎょろぎょろと覗く瞳のように待ち構えている。
可能性として、脳裏にちらつかなかったワケではない。けれどそれは「有り得て欲しくはない、最悪の可能性」のひとつだった。
「ずっと妬ましかった、憎らしかった! さあ……――私よ、消えろ!!」
それは宇宙を滅ぼす悪意の根源。
それは世界を墜とす輪廻の仇花。
想像――もしくは創造し得る限り最悪のダーカー【深遠なる闇】が、私たちの前に立ち塞がっていた。