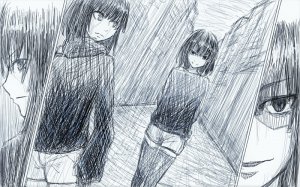小説『Endless story』#10-2
- 2017/07/19 05:49
- カテゴリー:Endless story, 小説, PSO2, ゲーム
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#10-2【全ての人の魂の戦い】
「ダッシュパネルとカタパルト投下を完了したわァ」
「こっちも揚陸艇操縦をマニュアルに切り替えたにゃん」
「揚陸艇の遠隔操縦は任せたわよォ」
「委細承知、だにゃ。アーテル、そっちもそろそろ頼むにゃあ」
「任せてちょうだァい」
作戦区域の上空に、際立って大きな機影があった。
それはアルトが独自のツテによって仕入れた、大型のキャンプシップである。通常兵装は無論のことA.I.S.の格納、そして大規模作戦のオペレーティングまでも可能にするという……本来は非合法、かつ非現実的な性能を誇る機体だ。
いくつもの青白いエアディスプレイが、忙しなく戦況を映し出す指令室で、アーテルとアルトは別の戦いを繰り広げていた。
アーテルがインカムのマイク部分を口元に寄せる。
「今回のオペレーティングはアタシが担当するわァ。事前に伝えた通りI・DFは削り切ることに執着しなくて大丈夫よォ。特に【若人】と【巨躯】の部隊は覚醒したら巻き込まれないよう注意してねェ」
さて、ここでひとつ整理しよう。
世界群歩行者達、DFCo、パラノイドサーカスの合同部隊で成された前線は、現在幾つかの部隊に分けられている。
まずウィリディスが隊長の「V隊」、アルーシュが隊長の「A隊」、ハイドが隊長の「H隊」、彼らは街の四方へ散ってそれぞれI・DF(ダークファルス)と対峙するための部隊である。
次にミツルが隊長の「M隊」は地上の、ヴェルシードが隊長の「W隊」は空中に蔓延るダーカーを端から殲滅し、他班の負担を出来る限り削る。
そして敵戦力を分散させたまま、団長が率いている「K隊」が大元である透藤縁を叩く。
これが作戦全体の構図と、分けられた部隊の全てだ。
「帰ったら白狐ちゃんと只野ちゃんが、おいしいご馳走を用意してくれているわよォ! しっかり勝って全員で帰ること、いいわねェ!?」
「さあ野郎ども、祭りの始まりだにゃ!」
♪
「ぬゥん!」
スプラウトの力強い一閃が、クラバーダを両断する。
空中のみならず、地上までもI・ダーカーの軍勢で覆われていた。しかもどこから沸いてくるのやら、倒した傍から現れるのでキリがない。息つく間もなくソルダ・カピタ数匹の隊列に切っ先を向ける。踏み込んで、再び振り抜いた刃の軌道。
安堵からか息を切った、わずかな空隙に。
「スプラウト、危ない!」
「むッ!?」
レティシアの金切り声に振り向く。跳んで迫るはウォルガーダ。
背後からの急襲に体勢を立て直す間もなく、万事休すかと思われた。
「馬鹿は馬鹿らしく――……」
しかし人影が落下する。
ウォルガーダの背部に大剣が深々と突き立つ。
「馬鹿なことでも、してろッ!」
地面に叩きつけられたウォルガーダは、断末魔を上げるコトさえ叶わず両断された。
黒いジャケットを着込んだ短髪の青年は、ウォルガーダに突き刺さった大剣を引き抜き、未だこちらを睥睨するI・ダーカーの大群に向かって睨み返す。
スプラウトとレティシアもまた並び立つが、戦況を見据える表情は険しいままだ。
「間一髪でした。礼を申し上げますぞ、ミツル殿」
「後で良い。今は1匹でも多く狩るのが先だ」
「とは言っても……これじゃ根本を止めない限りはジリ貧ですね」
短髪の青年、ミツルは「構うものか」とでも言わんばかりに大剣を構え直し、全身に力を込める。大剣「ザンバ」の切っ先が、獰猛な獣の牙を連想させるほどの気迫を纏った。
♪
「……――ホーミングエミッション!」
フナが構えたスカルソーサラーの銃口から放たれた、都合6つの弾丸がそれぞれ寸分も違わずに飛来する有翼系I・ダーカーへ着弾した。
ウィリディスやマーミンと共に地上へ先遣を任された、さしものフナとも言えど、この物量の前には辟易とせざるを得ない。このままであれば、いずれ押し負けるだろう。
けれど今はただ仲間を信じ、自分の成すべきところを成すしかない。思考を切り替える。短く息を吐く。再び眼前を見据えまた放たれる一射が、流星のように夜空を切り割いた。
直後に頭上から差し込んだ影。エル・アーダの奇襲である。
「ヴェルシードさん」
「オーケー!」
連なって響いた銃声が、エル・アーダの腕を、頭部を、コアを次々に砕いて撃ち落とす。
銃声の主、ヴェルシードは双機銃を弄び、振り向かずに銃口を両脇から背後へ向ける。さらに響いた快音と、次々に落ちてゆく黒い残骸。
「的が多いっていうのは良いコトだ」
「油断は禁物ですよ。次に行きましょう」
M隊とW隊はさらにメンバーを分散した上で、アルトが各地へ配置したダッシュパネルとカタパルトを利用し、作戦区域内の遊撃を敢行していた。どのみち市街地を舞台にしている以上は長期戦の選択肢など無い。それゆえに選べた、少数での遊撃という手段である。
つまり長引けば歴戦の世界群歩行者達とて危うい。勝負はいかに速く囚われのメンバーを救出し、いかに早く透藤縁を無力化するかにかかっていた。
♪
そして透藤縁との対峙を目的とするK班は、同じくダッシュパネルとカタパルトを使い、ビル群の屋上を伝って北へと駆けていた。
カナトの一撃がブリュンダールを屠る。ナーシャの一閃がダーガッシュを貫く。ワサトの双小剣がソルザ・プラーダを斬り落とす。
「ふうッ!」
ユカリが身の丈よりも長い刀……――「アカツキ」でゴルドラーダを仕留める。
各班がI・DFをはじめI・ダーカーの軍勢を引き受けているお陰で、K班を阻害する敵の数は比較的少なかった。ブレイクスルー的に雑魚を蹴散らし、駆け抜けては突き進んでゆく。
順調とも思える中で、しかし塊素だけは何か思案するように表情を曇らせていた。
「団長、どうしたん?」
「いや、あまりにも敵が少ない気がしてね。少なくとも他の隊の持ち場よりも……」
実際のところ、その違和感を抱いていたのは塊素だけではなかった。ナーシャと恋詩も頷き、ライレアは何も言いはしなかったが、普段の気が抜けた表情もどこかへ消え去っていた。ただ警戒するように前方を見据えている。
彼ら、彼女らが感じた違和感は正解だったと言えよう。
上空から降り立った威圧感に、ユカリとカナトはよく覚えがあった。棘々しいフォルムに大きな一対の触腕が目立つ。細かく振動する羽音は、その巨大さゆえに肌を震わす。
カナトが牙を剥いて、その巨影を睨み付ける。
「……ぃよう、また会ったな。久しぶりじゃねえか」
それは漆黒の体躯に、紫の紋様が刻まれたダーク・ビブラスだった。
さしずめI・ダーカーのユガ種とでもいったところだろうか、そいつは耳も覆いたくなるような絶叫を辺りに振り撒く。おそらく他の場所よりも戦力が手薄だった理由とはこれだ。
主戦力をI・DFに割かせた上で、I・ダークビブラス・ユガの相手を、自身を狙う本隊に担わせるという魂胆なのだろう。
「ナーシャ、ワサト、お前ら俺と一緒に残れ! ユカリと団長たちは先に向かえ!」
カナトが即座にコートエッジの切っ先を巨影に向け、切羽詰まった語勢で言い放った。決して容易い相手ではない。だがここで全員が足を止めれば、それこそ透藤縁の思うツボであるとすぐに看破したのだ。
「でも、カナトさん!」
「さっさと行け、お前が決着を付けるんだろ!」
塊素がユカリの肩を軽く叩く。ユカリが振り向くと、彼は黙って頷いて、前方へ目配せする。トーニャとライレア、それから恋詩も無言のうちに了承して先に駆け出す。
アシリアはユカリと同じく幾らか逡巡していたようだったが、すぐにユカリの手を引く。ユカリはアリシアの目を見てから、思い直したように口を真一文字に結んだ。
そして振り返らずに、再び走り始める。
カナトは彼女らの背を見送ると、やれやれといった調子で溜め息をついた。
「それでニャンボ、お前も行かなくていいのか?」
「この人数、さすがに少なすぎます。皆さまの盾となりましょう」
「そうかい。頼りにしてるぜ」
言いながら、カナトは武器をコートダブリスに持ち替える。ナーシャは抜剣の柄に手を添えて、巨影に向けて半身の体勢を取った。ワサトは両手に携えた双小剣を軽く握り直す。ニャンボは大剣を握りしめた指先に、一層の力を込めた。
「さあ……やるか!」
♪
エスカタワーの頂点は、遠くから見るよりもずっと大きな広場となっていた。あるいは展望台とでも呼んだ方が正しいのだろうか。
とにかく私たちが辿り着いたとき、縁は静かにそこで佇んでいた。
彼女はゆっくりと振り向いて、あらゆる光を排除したような眼差しで、流し目に私たちを一瞥した。表情は嗤っているようも、泣いているようにも、怒りで満ちているようにも、憂いているようにも、何の感慨も抱かない無表情にも見える。
「思ったよりは、早かったね」
風の音と、遠くで鳴り響く戦いの音だけが聞こえていた。私たちはそれほど静かに縁と対面している。しばらく睨み合っていたが、やがて縁は唐突に空を仰ぐ。
つられて私も上空を見上げた。ここだけはダーカーに覆われていない、見慣れた東京の夜空が見えていた。色はミッドナイトブルーより少し深めの黒で、星は少ない。まるで縁の瞳のようだった。
「私がI・ダーカーをどれだけ作ろうが放っておいて、アークスだけ救出すればよかった。なのにあなたたちアークスがそうしなかった理由、当ててあげよっか」
また縁は私を見ると、皮肉げに、あざ笑うように、あるいは自嘲気味に微笑んだ。
「私さ、もう何もかもどうでもいいんだ。この街とか世界とか。それが分かっていたから、放っておいてもきっと私が、色々とこの街のぜーんぶさ、壊しちゃうと思ったんでしょ? それ、当たり。乗ってこなかったらそうするつもりで居たから、ノリ良くて助かったよ」
ともすればからかうような、談笑するような軽い口調で彼女は話す。
そう、縁にとって全ては既にどうでもいいのだ。
ここでアークスが縁の宣戦布告に応じなければ、I・ダーカーの軍勢をもって、無意味にこの街を破壊しつくしただろう。その先に待っているものがマザーによる粛清であろうが、縁にとって大した抑止力にはならない。ある意味、むしろ彼女はそれを望んですら居る。
だから私たちはこうして縁の宣戦布告に乗らざるを得なかった。
今の彼女にとって重要なのはただ一点、自分が誰かに認められること。
「別に私が死んだって、周りがどうなったって、あんまり興味ないんだ」
「誰も認めてくれない、相手にしてくれないのなら、この世界に生きている値打ちなんて無いから?」
「……うん、正解。さすが私から生まれただけあるよね」
うすら笑いを浮かべたまま、縁はため息をついた。
それから右手にはイマジナリー・ボードを握りしめたまま、左手は額に当てて、乾いた笑い声をこぼし始める。イマジナリー・ボードはだんだんと強い闇色の光を帯び始めて、静かだった周辺の空気までもが震える。
それはエーテルの震えだった。青黒い粒子が縁を中心に渦巻き、鼓動のような音を伴い、彼女を「核」として巨大な像を結んでいく。
「だから私が認められるために、私の存在意義のために――……」
強烈なエーテルの暴風に、吹き飛ばされないように足元を踏ん張りながら、眼前を腕で覆った。風圧が弱まった頃合いを見計らって、私は眼前のそれを見上げる。
ダークファルス・ダブル。極彩色のカラフルな巨城に似た、邪悪の化身が屹立していた。
「……――ここで、まとめて私に殺されてちょーだい?」