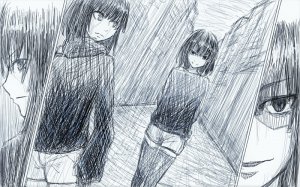小説『Endless story』#2-4
- 2016/06/01 05:44
- カテゴリー:Endless story, 小説, PSO2, ゲーム
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#2-4【俺の話を聞け】
チャレンジクエストは『VRエネルギー』がゼロになると、その時点の進行度で強制終了される。そしてVRエネルギーは時間経過か、クエストに参加しているアークスが1回戦闘不能になるたび減少していく。
「あそこ乗り越えれば最終エリアだったんだけれど、惜しかったねぇ」
あっけらかんと笑うアルーシュ。
ふたたび戻って来たチャレンジロビー。結局のところ、チャレンジクエストの踏破とは相成らず『ファルス・ヒューナル』によって阻まれた。
魚介系ダーカーを統べる王者『ダークファルス【巨躯】』の化身。その絶大な力を前に、私は為す術もなく圧倒されたのだ。
そして最終的に私ひとりが何度も戦闘不能を繰り返して、VRエネルギーが大幅に削られ、あえなく強制終了となった。
明らかに、私が足を引っ張ってしまった形だ。申し訳なさと気まずさから、なんとなく目線を下げて機械的な床を見つめる。
「ごめんなさい」
「そうね、勝手にひとりで突っ走り過ぎだわ」
ぐうの音も出なかった。
私ひとりが勝手に戦ったり死んだりする分には何も構わないのだろうけれど、もしこれが本当の任務で、彼女らの足を引っ張ったりするのはあまりに忍びない。
ちらと視線を上げて、ルベルの表情を伺う。案の定、平時に増してむすっとした表情で腕を組んでいた。
やっぱり視線をもう一度床に戻すと、彼女はひとつため息をついて頭をかいたようだ。
「……言っておくけれど、わたしがイラついてるのは足を引っ張られたからじゃないわよ」
「え……」
ではなぜだろう。もう一度視線を上げてルベルを見るも、彼女はすでにこちらから視線を外していて、それ以上を答える気はないようだった。
「まあまあ、むしろ初見であそこまで動けたんなら充分やで。ただVRとはいえ、もう少し自分を労わっていこうな?」
「は、はい……あれ?」
言われて返事をするが、ところでさっきまでこんな白髪に褐色肌の青年は居たっけ?
「ああワイやワイ、abe-c」
「えっあっはい、えっあれあのあれ?」
abe-cってあれ、さっきの黒いボディに赤いラインが特徴的で、バウンサーの武器を使っていたキャストじゃなかっただろうか。
「キャストの中には、一般生活用ボディと戦闘用ボディを使い分ける奴が居る。かくいう俺もあべしもその一人というワケだな。ちなみに俺はハイドだ」
「マジですか」
紫髪で、モノクルを付けた男性から明かされて思わず返す。
「改めてよろしくなー。あ、ワイのことは気軽に『あべし』って呼んでくれてええで」
「俺は……そうだな、そのまま『ハイド』でいい。よろしくな」
「はっ、はい……よろしくお願いします?」
なんというか、なんとなく好対照なふたりだと思った。そういえば戦闘用ボディの時もカラーリングがちょうど対になるような感じで、印象的だったっけ。
それにしても……特にあべしの方は、戦闘中と随分印象が違う。あの龍族を次々に薙ぎ倒していたキャストは、こんなにもフランクだったのか。
「やはり地球人だからか、ひとつひとつの反応が新鮮ですね。ユニークです」
「あれ……AAA3rdさんはそのままの格好なんですね」
「先ほどもハイドが申し上げた通り、一般生活用ボディと使い分けるかは個人の裁量ですから。それと、私のことも『あああ』と呼んでくれて構わないですよ」
「あ、あああさん……」
言っちゃなんだけど、適当に名付けられた勇者みたいな名前だ。
「それよりも、フォトンを扱う感覚については掴めたようですね」
「あ、はい、多分」
「多分……?」
実を言うと、キュクロナーダのカウンターを喰らってから後、クエストが終了するまでずっと奇妙な感覚で居たのだ。まるで、自分の意思で動いているハズなのに、誰かの意思と自分の意思が混じっているような。
アレが『フォトンを扱う』感覚だったのだろうか。いや、なんとなくではあるけれど、それとはまた違うものであるように思えた。どちらかといえばあれは、自分を『使われている』ような感覚とでも言った方が、しっくり来るように思えた――。
――あれ、自分は今、何を考えていたんだっけ。
「ユカリ、どうかした? 突然ぼうっとしちゃって」
アルーシュの声で、ハッと我に返る。少しだけ呆けていたらしい。
「いえ、何でもないです。大丈夫です」
あわてて、ひとまずそう返事をする。
何か言うべきことがあったような気もするけれど、思い出せないのなら大したことではないのだろう。
きっと疲れも溜まっているのだ。何しろこの数日で、色んなことが一気に起こったから。先ほどまでだって、VRとはいえ訓練へ向かって来たばかりなのだし。
それらを伝えると、アルーシュはしばらく考え込む。そしてひとつ柔らかく柏手を打ち、思い出したように言う。
「ユカリ、お昼の予定はもう決まってる?」
「いえ、まだ特には」
そういえば、もうそろそろそんな時間になる。訓練で疲れたからか、いつもより割増しでお腹が空いているような気もした。
「じゃあさ、一緒にフランカ'sカフェでランチにしない?」
「――『フランカ'sカフェ』?」