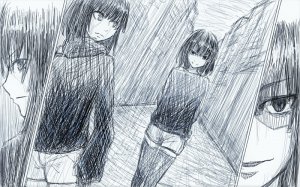小説『Endless story』#10-4
- 2017/08/02 08:12
- カテゴリー:ゲーム, PSO2, 小説, Endless story
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#10-4【透藤縁】
「私」が世界群歩行者達に馴染むことは、計画の要だ。
それを最初から分かっていたはずなのに、私は「私」が受け入れられていくたび、自分の中で暗い感情が沸き起こっていくのを確かに感じた。どうしてその場に立って居るのが、私じゃなくて「私」なんだろう。どうして紛い物の「私」は、ここまで想われているのか。
胸の奥で荒ぶる嫉妬は、黒い炎のかたちをしていた。
こんな簡単に受け入れてくれる居場所があるだなんて、こんなにいい人たちが居るって、最初から知っていれば……。
マザーに認められたい一心で、マザーの敵だからと、彼らを敵に回したことを強く後悔した。アークスの第9番艦に所属する、チーム「世界群歩行者達」を。
良心の咎めが無いワケではない。本来ならば私が彼らを憎む理由も無いし、彼らの良いところも「私」を通して見てしまった、聞いてしまった、知ってしまった。
けれど今更になって引き返すことも出来なくて、ただ私自身の浅はかさを呪うしかない。
きっと私は負けるのだろう、それすらも頭では分かっていた。侵食性能を持たないコトが象徴するように、I・ダーカーの性能は本来のダーカーに比べ劣っているのだ。
ダーカー退治の専門家たちを前に、それはどれだけ致命的な事実だろうか。
もし負けたら、マザーの役に立てず、オラクルも敵に回した私の居場所はどこにあるのだろうか。考えたくはないけれど、そんな簡単なこと、考えたくなくても分かってしまう。
けれどもう、おそらく私に勝ち目はない。
だから私は「私」を殺して、自分が正しかったんだと証明するしかない。
どんな道を歩んだって、私は幸せになんてなれなかったんだと悟ることが出来れば。
自分が生きる世界のどこにも、良い事なんて無いんだって思うことが出来れば。
……――そうして諦めることが出来れば、ちょっとだけ楽になれるから。
「逃がさない」
手のひらにエーテルを集めて、思い切り叩き付ける。
しかしトーニャがペットを……マロンを構え、衝撃ごと私の一撃をなんとか受け止める。
「下らない……!」
次に右腕で横に薙ぎ払い、衝撃波を生み出す。
さらに右腕、左腕と叩き付けて、拳を合わせて思い切り振り下ろした。
自らを【深遠なる闇】に変えた私に比べ、あまりにも小さい彼ら彼女らは、しかし一片も怯まずに相対する。私の攻撃を避け、あるいは防ぎ、私は少しずつ、けれど着々と追い込まれてゆく。
「……堕ちろ!」
エーテルを溜めて解放し、さらにレーザーの追撃。
しかしそれさえも決定打にはならず、ライレアはエーテルの波を正面から突っ切った。抜剣により放たれた一閃は、私が纏っているエーテルを大きく削り取る。
けれどまだ負けてやれない。別の場所でI・ダークファルスたちを倒した増援が来る前に、少しでも戦力を削るんだ。
エーテルによる光の柱を何本も、何本も、何本も辺りに降らせる。
しかし「私」は攻撃の合間を縫って、駆け抜けて躱す。
私が作り出した時よりも、今の「私」は格段に性能が上がっていた。身体能力を始め、全てが跳ね上がっている。それはあの時「私」が私の支配を跳ね除けたことと関係があるのだろうか……今は考えても仕方がない、と結論付けた。
「死んでしまえ!」
眼前まで飛び込んできたユカリへ、8つの眼球のようなビットを差し向ける。どれだけ能力が上がっているといっても、成長しているといっても、この数から放たれるレーザーの掃射を受けて無事なワケがない。
「エルダーリベリオン!」
しかし次々と撃ち抜かれ。粉砕される8つのビット。
団長の双機銃による連射が正確にそれらを射抜いたのだ。思わず歯噛みしたくなる。
「ハトウリンドウ!」
生まれたわずかな空隙。横合いから私へとさらに幾つもの剣戟が叩き込まれる。見れば高速で接近してきた揚陸艇の上に、青い長髪を揺らす女剣士の――ナーシャの姿がそこにあった。
I・ダークファルスのみならず、I・ダークビブラス・ユガまでも倒されたのかと気付く。このままでは形勢が大きく傾いてしまう――そう判断した私は、左手にエーテルを込めてレーザーを雨のように掃射する。
「イグナイトパリング!」
しかし遮ったのは、青い髪に赤い軽装の青年カナト。ナーシャに襲い掛かるレーザーの全ては、高速の剣舞によって叩き落とされ弾かれる。
ならばと右腕を振るう。辺りに無数の光球をばら撒く。ナーシャとカナトを始め、相対する全員が防御のために攻勢を少しの間だけ止める。
今が、今こそがチャンスだ。
私は両腕をかざした。エーテルが収縮し、辺りの重力を歪めるほどのエネルギーが一点へと集まってゆく。一気に全員を制圧して、流れを変えるんだ。
「させません、フォトンブラスト・イリオス・プロイ!」
全力で跳躍し向かってきたアリシアは、膨大なフォトンを手のひらに集め、解き放ち、そして喚び出す。それはまるで、右腕に赤い剣を携えた神々しい獣人だった。
アリシアは両手に携えた飛翔剣を、獣人は赤い剣を思い切り振り抜き――渾身の一撃で、私ごとエーテルの塊を叩き斬る。
リバウンドと衝撃で一瞬だけ思考が飛ぶ。大きく体勢を崩す。
「サテライトカノン!」
そして大きくのけ反った私に、上空から光の束が降り注いで襲い掛かる。
声の方へ向く。視線の先に見えたのは、青のフォトンラインが目立つ黒いキャストの姿。別のビルの屋上で、長銃を構えたハイドがそこに居た。
ああ……これは、まずい。
「また少しだけ力を貸しなさい、ステラ。セイクリッドスキュア零式!」
さらに追撃の槍が横腹へ突き立つ。
それは黒く禍々しいオーラを纏う、真紅の槍だった。槍が飛んできた先にあった揚陸艇から、片腕をまるでダーカーのように変貌させたルベルが見下ろしている。
形勢は火を見るよりも明らかだった。不利なんていうレベルを通り越していた。
だけれど、それでも、なんとしてでも「私」だけは負ける前に殺す。私は「私」を否定しなければならない。
……――でなければ、私が選んだ道の、全てが間違っていたことになるんだ。
胸元の巨大な眼球を思わせるコアから、これまでよりも更に太いレーザーを撃ち放つ。それはビルの屋上の床ごと巻き込んで「私」へと伸びていく。
「ヒーロータイム・ブライトネスエンド」
空中を奔った淡い緑色の閃光。
圧倒的なエーテルの密度を誇るレーザーは、それ以上に鋭く重い一閃で引き裂かれた。私と「私」との間に降り立ったのは、自身の背よりも大きな剣を携えて黒いコートに身を包んだ、右目が緑色の青年だった。
かつて私を助けてくれたこの人までも、私は敵に回しちゃったな。この窮地に立たされ、零れたのは自嘲と諦観の笑み。
彼が放った二の太刀を、目で追うことは出来なかった。ただ自身の胸部でぎょろぎょろと覗いている大きなコアが、斬り落とされたことに遅れて気付く。
――崩れ落ちていく瞬間に、私は少しの間だけ白昼夢を見た。
マンションの屋上から見渡す世界には、灰色のビルが墓石みたいに立ち並んでいた。
ずっとずっと遠くまで、どこまでも続くその景色の中で、私と「私」が向き合っている。
きっと濁り切って酷く暗い色をしているであろう私の視線と、紫色に澄んだ「私」の瞳とが交錯する。
凹凸の地平線は空と隣り合っている事に気付いたけれど、きっとそれはどこまで歩いて行っても、交わることは決してないのだろうと思った。
「私は――……」
ゆっくりと「私」は口を開く。何を言おうとしているのかは、すぐに分かってしまった。分かってしまったけれど、聞きたくはなかったけれど、私は自分の耳を塞ぐことも、目を逸らすことさえも出来なかった。
「……――私は、あなたとは違う」
蒼褪めた空から突風が吹きつけて、私と「私」……いや、ユカリとの距離はどこまでも離れ、やがて見えないほどに遠ざかった――。
崩れ落ちる、私を覆い包む【深遠なる闇】。
再び目の前に、長刀を大きく振りかぶって、ユカリが飛び込んできた。その瞳は力強い意志と決意の光が宿っていて、まっすぐにこちらを見据えている。
「さあ、行きなさい――ユカリ!」
ルベルの声が聞こえる。彼女が叫んだそれは私の名前であっても、私の名前ではない。
出会った仲間たちに支えられ、自分に課せられた困難をも乗り越えて、敵と対峙する。まるで物語の主人公みたいな、私のそっくりさんがそこに居た。
けれど決定的に、私はあなたじゃない。
自分と違う道を選んだ「自分」が、欲しかった全てを手に入れている光景は、あまりに残酷だなと思った。
「……ああ、私も、あなたみたいになりたかったな」
その言葉は、自分でも驚くほど自然に紡がれていた。それがユカリに聞こえたかどうかは分からない。
ユカリが振り上げた長刀に、紫色のフォトンが宿る。刀身が歪んで見えるほどに高密度のフォトンを纏わせたまま、決定的な一撃は繰り出される。
「はぁぁぁあああああああああッ!!」
長刀は勢いよく振り下ろされた。切っ先が【深遠なる闇】の胴体を袈裟に抉る。閃いた一閃は、まるで紫色の雷のようだと思った。
身体のかなり深い部分まで通り抜けた感覚を確かに味わった。けれどエーテル体だからなのか、痛みはほとんど感じない。
ただ私を覆っている【深遠なる闇】の模倣は、ゆっくりエーテルの粒子となって霧散し、細やかな砂が風に吹かれるように消えていった。
♪
目が覚めた時、私はビルの屋上で仰向けに寝転がっていた。
夜明けが近いらしく、東の空が少しだけ明るくなり始めている。周りを見渡そうとしたときに、私を囲んでいる人たちが、世界群歩行者達の面々であることに気付いた。
ああ、そうか……私は負けたんだっけ。まだおぼろな脳みそが、ゆっくり覚醒していく。
「起きた?」
最初に声をかけてきたのはユカリだった。隣にはルベルとアリシアも居る。
私にトドメを刺すときの眼差しはどこへやら、心配そうな、不安げな面持ちで私の顔を覗き込んで来る。
「私を殺さないんだ?」
問い掛けるとユカリは驚いたように呆けてから、ため息をついて眉間を寄せながら言う。
「殺す理由、ないじゃん」
「あっそ」
素っ気なく返すと、ユカリはさらにムッとしたような表情を浮かべた。
周りでは、事後処理のためなのか他のメンバーたちが忙しなく動いている。どうやら、決着してからそう長い時間は経っていないようだった。
けれど私が彼らに戦いを挑み、そして負けたのは事実だ。
ぽっかりと、心に埋めようのない大きな空洞が開いている。悲しくも、悔しくも無くて、ただ忘我にゆらゆらと揺れていたかった。あれだけユカリに抱いていた嫉妬さえも、今は静かに、物言わず横たわっている。
「まだ、わたしたちと一戦やるかしら?」
「ううん。素直に負けを認めるよ、これ以上は面倒臭いし」
それは本心だ。
ルベルは拍子抜けした様子だったが、すぐに「そう」とだけ短く返してきた。アリシアもほっとした様子で胸を撫で下ろす。
そして他のメンバーたちも私から目を離している。
……――だからチャンスだと思った。
私の陰に隠れるようにしながら。素早くイマジナリー・ボードを展開する。
いち早くルベルが私の挙動に気付いたが、さすがに一瞬だけ反応が遅れた。
現れたダガンが私のすぐ傍に居たユカリへと襲い掛かる。
「危ないッ!」
すぐにルベルがユカリをかばったお陰で、彼女はなんとか無傷で済む。
けれど、それ自体は私にとってどうでも良かった。彼女たちの目を奪う、その隙を作り出すことが目的だったのだ。監視の目が緩んだ瞬間に、私は走り出して、ビルの屋上の端へと足をかける。
「何するつもり?」
ユカリが警戒を孕んだ声で、しかし静かに私へ問い掛ける。
「言ったじゃん。私さ、別に自分が死んだって、あまり興味ないんだ」
「……まさか」
どのみち私はマザー・クラスタの使徒から粛清されるだろう。もしくは役立たずの烙印を押され、お払い箱にされるのだろう。
どこからが間違いだったのだろう、それは分からない。けれど確かに、もう私の居場所はどこにも無い。私は、私を認めてくれたマザーの期待に応えられず、私を助けてくれるかもしれなかったヒトたちさえ自分自身で裏切って敵に回した。
残ったものは、私の生き方が間違っていたのだという、残酷な事実だけ。
もう生きる理由なんてどこにも残されていない。
良かったと思えるのは、私が死んでも悲しむ人はどこにも居ないということだろうか。
「ダメ、やめて――……!」
「……おやすみなさい」
夜明け前の撫ぜるような風が妙に心地よく感じる。
なので身体を宙に預ける時も、呆気なく踏み出すことが出来た。全身が浮遊感に包まれ、ユカリとアリシアとルベルの、驚いたような、あるいは焦燥感に満ちた表情が見える。
全身から力が抜けて、この世界からあらゆる音が消えたような気もした。心は不思議と悲しくも怖くもない代わりに、ひとりで寝る前のような安心感に満たされている。
重力に抗うことなく、吸い込まれるように私は落ちて行った。
私は天国と地獄のどっちへ行くのだろう。
どちらも信じてはいないけれど、そんな疑問が頭を過ぎった。