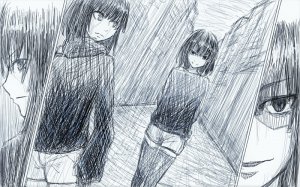小説『Endless story』#9-5
- 2017/06/21 08:41
- カテゴリー:小説, PSO2, ゲーム, Endless story
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#9-5【この世界のことだったら、大体分かったから連れて行ってよ】
「つまり今のユカリは、自律型の具現武装っていうことですか?」
「理論上はまあ、そうなるね」
アリシアが団長に問いかけてから、しばし驚いた顔。無理もないと思う、私自身も自分に何が起こったのか、説明するにはちょっと難しい。
縁が姿を消した後、私たちはひとまずチームルームへ集まって現状整理することにした。私の正体、透藤縁の存在と目的、そして私の身に何が起こったのか。
簡潔に言えば、私は自分の想像力とエーテル(もしくはフォトン)によって自分の存在を保っている状態らしい。つまり具現武装で自分の姿を象っているということだ。
「ちょっと自分でも何言ってるのか分かりませんね?」
「気持ちは分かるから安心してほしい。けれど、前例がないというワケでもないんだよ」
団長は空中にモニターを投影する。そこに映されたのは、軍服のような格好に身を包む青年だった。どことなく団長に似た見た目だと思ったが、一応は別人らしい。
「ハギト・フェムト。具現武装エメラルド・タブレットの暴走によって生まれた、自律型の具現武装だ。今のユカリさんはこれに近い状態と言っていい」
幻創種の軍勢を無尽蔵に生み出し、果てには超弩級の幻創種「幻創戦艦・大和」を使役するというハギト・フェムト。何度迎え撃とうが大気中のエーテルによって自己修復し、示威の為に幾度となく日本近海へと襲撃を繰り返す厄介な敵であるらしい。
おそらく私の自己修復も、同じ原理なのだろう。違うのは、ここはオラクルなので大気に満たされたフォトンを再生に使っているというコトくらいか。
自分の手のひらを見つめてから、チームルームの壁に体重を預けている青年を見た。彼も私の視線に気付いたのか、腕を組んでうつむいていた視線を、わずかに上げる。右目の眼光はチームツリーの色合いと少し似ていた。
団長が口を開く。
「ウィリディスさんとマーミンさんは地上における先行調査でハギト・フェムト、そして幻創戦艦・大和と何度も対峙していてね。そしてそれらの損傷部と撃破した時の感覚が、負傷したユカリさんの様子に酷似しているという報告を受けて、実はその時点で君の正体を察していたんだ」
「団長の推察を受けて、俺はひとつ提案をした。逆にそれを利用してはどうか、と」
すなわち逆に私を歓迎し、受け入れ、メンバーのひとりとして過ごさせることで、私を寝返らせてしまうという計画。それが団長とウィリディスの目論見だったのだという。
さらに兼ねてより縁に「サンプルとしての価値」を見出していた社長が一枚嚙むことで、ユカリを自律型の具現武装として再覚醒させる、というアイデアが生まれたらしい。
しかし一方で、オラクルに危険因子を招き入れるコトを危惧するメンバーも当然ながら存在した。そのため監視役としてルベルが常に私に付き添うよう指示していたのだ。
これが彼らの説明である。
「騙したような形になったことは謝る、すまないね」
歩み出て、静かな口調でゆっくりと頭を下げたウィリディスに少し戸惑う。
それらの事実を今まで私に隠していたのは、謝られるようなコトではない。むしろ私にとって大事な居場所を与えてくれた、その機会をくれたのだとも捉えられるからだ。逆に謝られると困ってしまう。
「そんな、謝らないでください。私もここへ来れて、そして皆さんと出会えて、結果的に本当に良かったと思っているんです。ただ、私が気になるのは……」
ただ、今の説明だけではどうにもしっくり来ない。なぜそこまで私に肩入れするのか、という点だ。私を味方につけ、マザー・クラスタや透藤縁の情報を聞き出すつもりだったにしても、そもそも私は記憶を消されていたのだ。それとも幻創種に対する新たな戦力として期待していたのか。いや、それこそウィリディスたちを見ている限り、それほど戦力に困窮しているとは思えないし、未だに私よりもここのメンバーたちの方がおそらく強い。
社長との契約は別にしても、私を受け入れるメリットに比べ、デメリットが大きすぎる。加えて私が縁の支配を跳ね除けた件についても、不確定な要素が多いと感じた。むしろ、それらはまるで「そうなって欲しい」という願望を含んでいるような。
「ウィリディスさん、あなたが本当に――……」
いったん切って、沈黙。言いたいことをまとめ、私はウィリディスを見据える。
「……――私を利用するためだけに、その提案をしたようには思えなくて」
ほんのわずか、一瞬だけ、彼の表情に驚きが浮かんだような気がした。
その反応で確信した。きっと向こうも私のことを覚えている。正確には、あれも透藤縁であって私ではなかったけれど、今の私は記憶の全てを彼女と共有している。
どうして彼はメリットの薄さを承知の上で私を助けたのか。見捨てなかったのか。その答えは、ある事実を当てはめることでひとつの像を結ぶ。
「……改めてお久しぶりです、ウィリディスさん。いつも助けられてばっかりですね、私」
「ああ、久しぶり」
「……どういうことだよ?」
疑問符を浮かべるカナトたちに向けて、今度は私が説明する。
私がダーカーに襲われてオラクルに運ばれた日より以前に、透藤縁はアバターを通じてウィリディスと出会っていたのだ。
右も左もわからなかった私……――いや縁が困っていたところに、たまたま声をかけたのが彼だ。その後も幾度か彼は縁を手伝うためクエストに同行し、時には相談に乗ったりなどしていた。
要するに何てことない、彼は見捨てなかったのではない――見捨てられなかったのだ。短い間とは言え、見た目が見知った相手だったものだから。その上団長の推察を聞き、I・ダーカーの存在を受け、私が縁の模倣体だというところまで予想できてしまったから。
「本当に、ありがとうございます」
「どういたしまして」
彼は簡潔に、素っ気なく返事をした。
無口で、無愛想で、無味乾燥なように見えて、相変わらずこの人は他者を放ってはおけないのだろう。
「横槍を差すようですまない。ウィリディス君がユカリを助けようとしたのも理解出来る。しかし現実的な問題の話もしよう」
進み出たのはハイドだった。
恰好は戦闘用のキャスト・ボディのままであり、銀色に鈍く光を反射する仮面の下から表情は伺い知れないものの、張り詰めた雰囲気を感じ取ることが出来た。
現実的な問題――すなわち社長、ルベル、そしてロゼの3人がダークファルス化され、縁の駒として囚われている現状についてだ。
「今までダークファルス、もしくはそれに準ずるモノへ転化し、無事にアークスへと復帰した例は2人だけだ。しかもそのうち片方は完全に変異しきっては居らず、もうひとりの例は正直なところあまりにも特殊」
ハイドがそれを追及するのも無理はない。囚われているのは、彼女の実の娘なのだから。私の隣に立つアルーシュも、少し目を伏せて唇の端を固く結びながら、じっと聞いている。
どうやって3人を救出するのか。それが目下のところ、何よりも最優先の課題だった。
「……――それなんですけれど、結論から言って救出は可能です」
しかしウィリディスは、きっぱりと断言した。
団長を除く一同に、少なからず驚きと動揺が広がる。ウィリディスが団長の方へ目配せすると、団長は無言で頷いてから私たちメンバーの前へと立ち、続いてアルトとアーテルもその隣に並ぶ。中空に浮かんだのは幾つものモニター。
「良いかな皆さん、よく聞いて欲しい。これから東京の市街地を守りつつ透藤縁を打倒し、そして拉致されたメンバーたちを奪還するため、そのためのブリーフィングを始めようと思う。ダークファルス化への対処についてもその中で詳しく説明するよ」
チームルームに響く団長の明朗な声。その言葉と共に場の空気が引き締まり、メンバーの意識が団長へと集中する。しかし団長の視線は、再び私の方へと向けられた。
「ただそのために、まずユカリさんと……そしてウィリディスさんに聞いておかなくちゃならないことが、いくつかある」
「……私、いや縁の目的と……どうしてアークス宣戦布告したのか、ですね?」
団長は無言で頷き、私もそれに応じた。
みんなの視線に晒されて少し緊張しながらも、私はひとつ深呼吸して、気持ちを整えた。上手く話せるだろうか、などと考えながら。でもみんなとこうして向き合えているのは、ちょっとした進歩かな、などとも思いながら。
「縁の目的は、マザーに認められることです」
♪
透藤縁は、望まれて生まれた子供ではない。
灰色の日々を快楽で誤魔化し続けた、若き2人の男女の産物。それが彼女である。
父親は母親が身籠ってすぐに2人を見捨てどこかへと逃げたまま、今も生きているのか死んでいるのかすら分からない。自分を孕ませた男に逃げられた縁の母親もまた、心中は混沌としていただろうが、それでも実の娘へ向ける悪意は並大抵のモノではなかった。
縁は常々「あなたなんて産まなければ良かった」と、そう言い聞かされ続けて育った。それでも縁の母親が彼女を養育し続けたのは、社会的な罰を恐れたに過ぎない。
浴びせられる罵声と振り上げられる暴力の毎日に、いつからか縁は泣き方さえも忘れた。当然ながら食生活もずさんであったので、17歳となった今でも彼女の背丈は低く、発育が遅れており、何より折れそうなほどに細い。
そして母親にも甘えられずに育ってきた彼女が、同年代とはいえ赤の他人と接する術も持たないのも道理だった。家では虐げられ、学校でも孤立し、縁は年端も行かない少女でありながら「自分はこの世界に要らないのだ」と強く理解してしまった。
縁が母親共々ダーカーの襲撃を受けたのは、彼女が14歳の時だった。
母親は命を落とし、自身も肩口から脇腹にかけて深く大きな傷痕を負った。傷痕は今も生々しく残っている。
祖父母も既に居らず、天涯孤独の身となった彼女は、遠縁の親戚たちの間をたらい回しにされた。どこの家庭も表面上こそは縁を受け入れるように振舞ったが、それが本心ではないことを、本来は聡明で頭の良い少女は理解してしまった。
そのため中学を出てすぐに、彼女は一人暮らしを始める。しかし誰の支援も借りずに、15歳の少女がたったひとりで学業とバイト、そして自分の生活を両立してみせるのは、決して易いコトではない。
高校を中退した彼女はバイトで生計を立て、目的も目指すべき標もなく生活を続けた。既に彼女は自分が生きようが死のうがどうでも良かったのだ。だからあの日、住んでいるマンションの屋上から、石のように固く冷たい世界の全てを見渡した。
恐ろしい、けれどそれ以上に待ち望み続けた一歩を踏み出そうとする直前、しかし踏み止まる。突如として中空から現れた「その人」に、ひとつの携帯ゲーム機を渡されたのだ。
母親の遺品と称され、渡されたゲーム機にインストールされていたのは、ファンタシースターオンライン2――略してPSO2と呼ばれるゲーム。なんだかよく分からないうちに言いくるめられなんとなく始めたそれには、既にプレイ用のキャラクターが作られていた。
それは、自分と瓜二つのアバターだった。
いくらかの疑問を抱きながら始めると、そこに広がるのは彼女にとって何もかもが新鮮な世界。元々からゲームの類に興味がなかったワケでもないし、それなりの知識を集めては居たものの、実際にプレイするのが初めての彼女にとっては充分感動的な体験だった。
しかしここで問題がひとつ――そう、本当に右も左も分からないのだ。
各惑星に降り立ってダーカーを倒すべし、というゲームの概要は理解した。しかし何をどこからどうやってどうすればいいのか分からない。
「……もしかして新人?」
挙動不審の有様で右往左往している彼女に声をかけたのは、緑色の右目が特徴的な黒いコートの青年だった。
その出会いからしばらくの間、縁は青年と共にクエストへ行くなどして共に過ごした。オンラインゲームの中とはいえ、ある意味で初めてまともに他者と接した彼女は、次第に悩みや相談ごとなども少しずつ打ち明けるようになった。
青年もまた不愛想で無表情ではあったものの、静かに彼女の言葉に耳を傾けた。
そして縁も青年が時折話す、オラクルに住まう彼の仲間たちの話に興味を持った。縁にとって彼を取り囲む個性豊かな仲間たちの話は、眩しくもあり、純粋に羨ましくもあった。
その時こそは縁自身が多数の人とうまく関わっていく自信がなかったため断ったものの、青年の「いつかみんなを紹介するよ」という言葉は、素直に嬉しかった。
そして縁がマザー・クラスタの一員として見出されたのは、その直後の話である。
生来の環境もあり、縁にとってマザーの言葉は、ひとつひとつ全てが自分の心を救ってくれるような心持ちだった。縁の全てを見抜き、その上で受け止めてくれた、自分の苦悩を、苦痛を、全て認めてくれた。言葉だけの存在は、けれど確かに縁を救った。
青年と、そしてマザーとの出会い。灰色の日々に光明が差し始めた縁だったが、しかしそんな彼女の前に、再びそのヒトは現れた。
縁に母親の遺品である携帯ゲーム機を渡したヒトである。
そして縁は全ての真相を聞いた。
オラクルが実在するのだというコト。
マザーはオラクルの存在を心から憎んでいるというコト。
PSO2はエーテルに適性のある人間を選別するためのシステムだということ。
そして選別された人間たちを集め、オラクルに復讐を果たすことこそが、マザーの悲願であるというコト。
マザー・クラスタの幹部たる「使徒」のひとりは縁に提案した。自身がマザーの目的にとって有益であるという明確な成果を示せれば、その席に加えても良い、と。
脳裏に浮かぶのは青年の姿と、何もかもが目新しくにぎやかなオラクルの世界。
そして未だ姿も見えず、しかし自分の全てを肯定してくれたマザーの声。
縁は激しい葛藤のうちに揺れた。
どちらかを取れば、どちらかを裏切ることになる。
どちらも初めて、それまでの人生になかったぬくもりを与えてくれた。まさしく希望の光で、これからひょっとして自分は少しずついい方向へ転がっていくのだろうか――そう思えた矢先に、こんな決断を迫って来るなんて。
悩み、苦しみ抜いた末に、彼女は結論を導き出した。
そしてその日以降ぱったりと、縁は青年の――ウィリディスの前に姿を現さなくなった。
♪
雨は止んでいた。
雲が去り始めた西の空は、鮮やかな焔の色に染め上げられている。影絵のようなビル群に紛れ、一際高くそびえているエスカタワーの上層階のふちに、縁は腰掛けていた。
I・ダーカーを生み出し、オラクルにさえ混乱の波紋を広げた張本人は、足をぱたぱたと揺らしながら小さく歌を口ずさんでいた。
「みーたい未来、じーぶん次第、そう、あきーらめないーかーぎりー……」
はたと動かす足が止まって、歌も途切れる。不意に物憂げな様子で遥か下の方に広がる街並みを見下ろしながら、縁は深く、深くため息をつく。
「……くっだらないなあ」
どこか投げやりな様子で言い捨てられた、たった一言の行く先は誰も知らない。
「でも、どう転んだってこれで最後だね」
両腕に力を入れながらぱっと立ち上がり、踵を返す。軽くショートパンツの裾についた埃を払いながら、一度だけ振り返ると空を見上げた。
睨み付けるようにも見えた双眸は、ただ奈落に続いているような漆黒を湛えている。
あとは何も言わず左右へ開いたガラス張りのドアに導かれるまま、少女はエスカタワーの内部へと歩いて行った。
Chapter9『Foolish hero』End.⇒Next『#10-1』