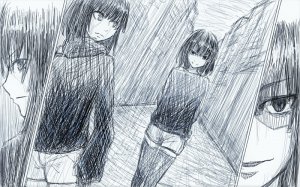小説『Endless story』#8-4
- 2017/05/03 07:08
- カテゴリー:Endless story, 小説, PSO2, ゲーム
- タグ:EndlessStory
- 投稿者:Viridis
#8-4【テルミーフールトークショーディアンドレイン】
「あなたたちは、兵器を作る企業……ですよね?」
「その通りだ」
ユカリが切り出した「取引材料はある」という言葉。社長は少し目を細めて応じたが、しかしそのプレッシャーは変わらない。アーテルは固唾を飲んで、何も言わずにユカリを見守る。アルーシュはあくまで平静を貫いたまま、行く末を見守る。
ユカリは物怖じしながらも、それを抑えつけ、あくまで社長と正面から対峙する。
DFco.は軍需産業であり、兵器の開発を行っている企業である。それはここへ来る前に、アーテルから聞かされていた。取り分け対ダーカー兵装におけるノウハウと、その特許の数に関しては、数あるオラクルの兵器ブランドにおいても随一だ。
では、その特許とノウハウは、いかにして得られたモノなのか?
「そして……――その技術の大元は、社長自身によるもの」
「……少し喋り過ぎだ、研究者」
「ごめんなさいねェ、必要なコトだったモノだからァ」
そう。目には目を、毒には毒を。ならばダーカーにはダーカーを。
ダークファルスである社長自身の力を研究し、武器や兵器として汎用化した。それが、DFco.における技術力の基盤である。エネミーを打倒する武装を作るなら、エネミーを研究し尽くしてしまうのが最も手っ取り早い。そのための研究サンプルが社長自身なのだから、そうそう他の企業には真似できるはずもない。
その結果、DFco.が市場トップを独走することになったのだ。
「では、幻創種に対する兵器の開発は、どうなんでしょうか」
幻創種は、近頃になって地上で頻出するようになったエネミーたちの総称だ。その性質はダーカーや各惑星の原生生物や機甲種、いずれとも異なり、地球人やアークスの恐怖や願望に応じて、どんな形にも変質しうる。そして打倒された幻創種は、すぐにエーテルとなって拡散してしまう。
登場がごく最近であることと、打倒された幻創種が拡散して消えることから、ユカリが立てた仮説はこうだった。
「おそらく、オラクルの軍需産業は、どこも幻創種への対応が遅れているのでは?」
研究サンプルの不足。
ほう、と社長がこぼす。その目が更に細められる。元々の人相の悪さもあって、威圧感は増大する。しかしユカリは、あくまでも主張を続ける。
「地上で発生している幻創種は、アークスとしても看過できない問題だと聞いています。逆に言えば、対幻創種の手段も、それだけ需要があるってコトですよね?」
ユカリは知らない……――いや、ユカリが独房に囚われているとき立てた、自身の仮説が確かならば、むしろユカリ自身の記憶から消されていると言った方が正しい――……が、マザー・クラスタなる集団も、その騒動の裏で暗躍している。マザー・クラスタの正体も目的も依然として不明のままだが、アークスに対して何かを仕掛ける気なのは明白だ。
幻創種への対抗策は需要があれど、遅れている。ユカリの発言は的を射ていた。
「そのために必要なのは、幻創種の研究サンプル。そして、ここに居ますよね。……――その研究サンプルになり得る存在が」
つまり……――ユカリの言う取引材料とは、自分自身である。
自身が研究サンプルとなること、それがDFco.にとっての利益となる。
それがユカリの主張だった。
「だが貴様は暴走する。ダーカーを呼び、アークスをダークファルスに変える」
「その通りです。だから、社長がそれを制御するための術を教えるんです」
社長がユカリに、ダーカーとしての力を、抑えつけ制御する術を教える。それ自体が、DFco.自体の利益となる。それが、ユカリが言う取引材料の全容だった。
アーテルの頬に冷や汗が伝う。アルーシュのバインダーを掴む指先に少しだけ力が入る。ユカリは声も固く握った拳も震えながら、社長を見上げる。社長は品定めでもするように、あくまで射殺すような、冷徹な視線でユカリを見下ろす。
社長室に広がる静寂は、長いようにも短いようにも思えた。とにかく肌を刺す緊張が、しばらく辺りを席巻していた。
やがて社長は押し殺したような嗤いを洩らす。ユカリは少しだけ驚いたのか肩が跳ねる。
「……面白い小娘だ。あの青年が、家主が見込んだだけはある」
ダークファルスという存在は、特定の「何か」に執着する傾向がある。
たとえば【巨躯】ならば闘争、【敗者】ならば知識、【若人】ならば若さと美貌、【双子】ならば破壊と享楽ひいては【深遠なる闇】の復活。
そして社長が内に飼うダークファルス【群狼】ならば、生存すること。
生存とは、生命活動を持続するコトではない。己が生きる理由を示し、自覚し、それに殉ずるコトである。だから社長はDFco.を設立した。だから社長は働き続けている。己が、生きる理由を示し続けるために。己が生き続けるために。
だからこそ、ユカリが「死にたがりの少女」のままならば、斬り捨てようと考えていた。
しかしどうだ。実際に対面した今の彼女は、死にたがりとは程遠い。生きるための意味を見つけた。生きるために、現在の自分に出来る最善の術を考えた。そして、恐怖と威圧を受け止めながら、それを遂行してみせた。
ならば、それに応えぬ方が恥というモノだろう。
「良いだろう、小娘。貴様の取引に乗ってやる」
社長は、牙を剥いて言った。元々の人相が悪いため、どこまでも凶暴な笑みだった。
アーテルと、アルーシュまでもが安堵のあまり溜め息をつく。
ユカリも安心のため息を漏らしながら、どことなく力の抜けた調子で肩を落とした。
「社長、アナタ試したワねェ?」
「ああ。この小娘がただの甘ったれで腰抜けならば、斬り捨てるつもりで居た」
社長は、ユカリという存在のメリットも最初から承知していた。むしろ社長から、DFco.に研究サンプルとして引き入れる選択肢も存在していた。
数日前……ユカリが独房へ入る前に、DFco.の面々が世界群歩行者達のチームルームへと現れたのは、アーテルの手引きにより彼女の研究サンプルとしての価値を見定めるつもりで居たからだ。
しかし社長は、自ら生き抜こうという気概を持たない者を唾棄する。ただ現実的な手段を持たず、理想論だけ語る愚か者も論外だ。どれだけユカリ自身に価値があろうと、その2点において気に食わなければ、社長はユカリを見捨てる気だった。
そしてユカリは今、見事にほかならぬ自分自身の力で、自分がどちらでもないと示した。それは、自分自身の力で証明する他にない。それをよく分かっていたからこそ、アーテルもアルーシュも余計な口を挟まなかった。
こんなに上機嫌そうな社長を見るのは、いつ以来だろうか。アルーシュはそんな感想を抱きながらも、しかし後が怖いので、何も言わずに黙っておく。
「だが……――残念ながら、悠長に小娘の相手をしている時間は無さそうだな」
社長が不意にそれを言うのと同時、ユカリから青紫色の力場が噴出する。
それはロゼやルベルがダークファルスへと変貌した時のそれと同じモノだった。ユカリが頭を抱え、アーテルとアルーシュは噴き出た圧力に後ずさる。
「くそっ……出て来ないでよ! これ以上、私の身体で……好き勝手しないでよ!」
ユカリは抗うように叫ぶ。悲痛で必死な叫びだった。しかし間もなくそれは途切れる。
青紫の圧力を撒き散らして、頭を抱えながら、再び社長の方を向くその視線は、しかしもはや別人のそれだった。まるで、底なしの絶望からこちらを覗くような。
「……――へぇ。あなたもダークファルスなんですね」
「ようやく尻尾を出したか」
社長はあくまでも泰然とした様子で、ユカリ……いや、ユカリであってユカリではない「何か」に向けて言い放つ。
そして、今度はまぎれもなく、ユカリ自身に向かって忠告した。
「小娘、聞こえているのだろう? いいか。今、貴様の身体を支配しているソイツに注目しろ。目を逸らすな。そして正体を探れ。ソイツが……――全ての元凶だ!」