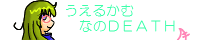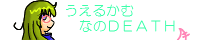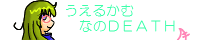第一章 猫を恐れし犬
グリーンピース――栄養があるのは分かっているがどうしても食べられない我が侭の残骸。
1
この日も永谷園(ながたに その)は放置ミン市を歩いていた。
街は繁華街にも拘らず、誰一人として客引きを行わない。そんな雑然とした環境だった。
道には多くの露店が立ち並び、ごみごみとしていた。突風が吹いてはボロい露店が宙に舞う。
そう、かなりトリッキーな風景だ。
人の心は遠く離れている訳でもないのに街に活気は無く、様々な街の喧騒も聞こえて来ない。時折、聞こえてくるのは親父のくしゃみと、露店の店主の叫び声、そしてぴよぴよサンダルの音。しかし、活気のある叫び声はない。
いつも付いて廻る音は、園のぴよぴよサンダルのみ。
そこにはギャグがある。
全てを落胆させるギャグ。
それは人間がそうそう耐えられるようなものではない不快感、憤り――。
――ネタが変?
自分の心から浮かんで来た言葉に皮肉を感じて、園は街の中を独り、くっくっと笑った。
――ネタ? 面白いネタって、なんだ? 本当に全米を震撼させる事のできるものなど存在しうるのであろうか? 落ち着け、落ち着け。これはギャグなのだろうか?
たった独りでは大したこともできないくせに、何を偉そうにしているのだろう。ただ単に、偉そうにしているだけの人間ではないのか? 真理だ哲学だ科学だと言っている割りには、心霊特集のTV番組を見て、ガッツ石松の存在に落胆し〝痛い〟と感じる。彼は全然偉くないではないか。
それなのにガッツに比べて自分たちは偉いと思ってる。それが僕なのか――。
だとしたら、僕はなんなのだろうな。
僕はまだ新人でもない。もうすでにノイローゼではないのか。
だから、僕はこの街に来た。放っておいて欲しいのだから・・・。
にゃ~ぉ。
僕は吃驚した。この街に来てから誰にも話し掛けられた事がなかったのに・・・。
本当の僕は何かを求めていたのかも知れない。
△ ▼ △
猫に誘われるかのようにたどり着く。
そこにはある意味、パラダイスが存在した。
猫好きが好む臭い。ふにふにとした肉球。それらが混じり合っている。
もうすぐ夏を感じられる、脳内のアドレナリン。そして、まるで絵の中にいるかのような光景。
周りにあるものは元いた世界のそれである。しかし、雰囲気はまさに異界――。この空間にあるもの、感じるもの、臭うもの。全ては異界にあるべきものだ。こちらの世界にはないものだ。
こちらの世界のものでありながら、こちらの世界に属していない場所。猫のいる場所。
猫は既存の世界を浸食し、自らの住処を形作る。
猫が好む環境に。
猫が求める空間に。
猫が必要とする世界に。
別に驚くようなことではない。空間を自らの好む世界に変えるなんて事はこの世界で偉そうにしている人間だってやっている事だ。猫が自らの好む空間を作り上げても、それは何らとるに足らないこと。
猫は、古来より自由気侭の象徴として知られてきた。この科学のはこびる現代においても、それはさほど変わらない。
ギャグは猫に通じない。いくらギャグを並べようとも、猫から笑いを引き出せる事はない。
人間は知っているのだ。どんなにあがいても、猫は笑わない事を。
不安、孤独、哀しみ、憎しみ――。
どれだけ並べようとしても、人間である以上諦めを知っているのだ。なぜならば、生命が誕生する前から猫はそこにいたのだから。ずっと猫には言葉が分からない事を知っているのに、どうして笑いを取れようか?
つまりは――猫は、反応などしないということだ。
猫を笑わせるのは、言葉が見向きもされていないからだ。
では、なぜ猫は無視するのか。
答えは明快にして単純。
人間は勘違いをしているだけなのだ。
猫は人間の存在を、《存在》としては認めている。しかし、具体性を帯びた存在ではない言葉を認めてはいない。
それは単なる想像であることもある。しかし、猫の想像力は意外と侮ることはできない。
だが、そのことに気付いている人間は少ない。大抵の人間は、はなから諦めている。
しかし――
園は猫世界の中央に立ち、“神”が来るのを待つ。
猫の神様は有意義なことではある。自分の身と同化することに着眼すれば。
「――皮肉なもんだ」
園はようやく、音らしい音を発した。それはこの空間における、最初で最後のような声だった。それに続く声なき笑い。
いよいよ、神光臨!
神が“人間を求めた”のだから!
そこにいたのは、《猫の神様》。
キター(?∀?)ーーーー!
僕の周りにいた猫達は人間に近い形状へと姿を変え、詩(うた)という言葉を紡ぐ。
かーごめ かごめ
かーごの なーかの とぉりぃは
いーつ いーつ でーやぁるー
よーあーけーのー ばーんーにー
つーると かーめと すぅべった
うしろの しょうめん
だーあれ……
「――」
そして、園は小さくつぶやいた。
「その唄は安陪清明が作ったと言われている・・・」
彼等は、「へぇ~」
……鳴いていた。
△ ▼ △
「何でこんなところでガス欠なんだ」
ブルーハワイを基調とするアロハシャツの男が携帯でどこかに連絡をとっている。男がそれとなく辺りを見回すと、三輪バイクに跨った彼の仲間が呆れている。
そこには、ガソリンスタンドはない。行く先は彼方まで続くスーパーハイウェイの交点。
パトカーの音が聞こえた。やったー、助かった・・・。
もはや、そこに巣くっていた諦めはない。そこにはすでに音がある。光がある。気配がある。けれども、笑いはない。
「――はい。我々が到着したときには彼の車にはガソリンはありせんでした。レッカーをお願いします」
淡々とした口調で男が携帯に話す隣から聞こえてくるのは若い女の声だった。割りと早口だがはっきりとした声が運ばれてくる。
「――はい。ではあと1分で到着します」
そう女性警官は答えて、男性に免許の提示を求め、切符を切った。
警官はほとんど無駄のない動きで無言で近くに止めてあったパトカーに乗り込み、すぐにその場を立ち去った。
彼の車の上のポールで、オービスが監視していた。
オービスはレッカー移動された車を見つめ、車のライトが見えなくなるまで見届けた。
凹む男性を友達が慰めている姿まで、きっちりと。
単に点数を稼ぐために偶然を装って警察官は今日も走る――。
全く、情けない話である。
|